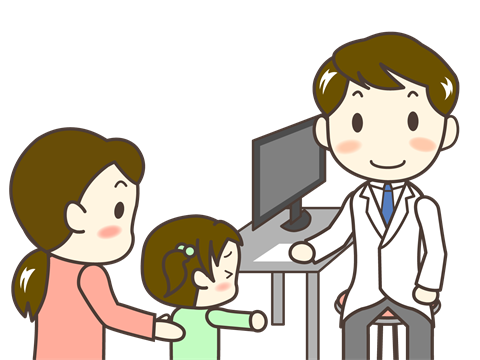
6月から7月に流行するといわれている手足口病ですが、今年は5月からすでに流行が始まっていて現時点で昨年の6倍もの感染者がいることが報告されました。
手足口病とはどんな症状が出るのでしょうか。
かかってしまったらどんな治療をすればいいのでしょう。
保育園は何日お休みすればいいでしょうか。そんな疑問にお答えします。
手足口病はどんな病気?
手足口病はウイルスの感染によっておこる感染症で子供を中心に夏(6月~7月)流行します。
それが今年は少し早く5月から流行が始まっています。
主に感染するのは子供ですが、その中でも90%前後が5歳以下の乳幼児なので心配も増してしまいますね。
「手足口病はよく聞く病気だし、病院に行かなくても大丈夫かな」などと自己判断はやめましょう。
手足口病はウイルス感染で主にコクサッキーウイルスA16やエンテロウイルス71が原因となっています。ですが「新手足口病」といって、今までのウィルスとは違うウイルスが原因となることがあるのです。
手足口病かな?という症状が出たら病院に行きましょう。
手足口病の症状は?
感染してから3~5日経つと手足口病という名前の通り、口の中、手のひら、足の裏などに水泡性の発疹が出ます。
全ヶ所に出る場合もあれば、一か所のみの場合もあります。ウィルスによってはおしりなど全身に広がる場合もあります。

感染者の3分の一ぐらいに発熱もありますが、高い熱が続くことはほとんどありません。
写真のような発疹がでたら病院を受診しましょう。
手足口病の感染源は?
飛沫感染、接触感染、糞口感染(糞便から排出されたウイルスにより口を通して感染すること)によって感染します。感染した子供と一緒に遊んだりすると感染する可能性が高くなりますね。
感染してから症状が出るまで3~5日なので、感染していて症状が出ない子供と遊ぶこともあるでしょう。保育園などで集団生活していたら、仕方のないことですね。
感染をできるだけ防ぐ方法がありますので、ぜひ実践してくださいね。
手足口病の予防方法
- こまめな手洗い
- マスクをする
- タオルの供用を避ける
ですが手足口病はほとんどの人が子供の時にかかって軽い症状で終わり、免疫をつけてきた感染症で感染してはいけない病気ではありません。もしかかってしまった場合は病院に行き適切なケアをしてあげましょう。
手足口病の治療方法
残念ですが手足口病には特効薬がなく、治療方法もありません。
薬が処方されるとしたら発疹の痛みを和らげる痛みどめや、熱が出た時の解熱剤など付随する症状の緩和のみです。
合併症がない場合は、感染症が治るまで自宅で安静にしてることが最も大切なことです。
ただ口の中などに発疹ができてしまうと、痛くて食べることが出来ない、水分を取ることもできない状態になるかもしれません。どうしても自宅で水分が取れない時は病院で点滴をしてもらい、脱水症状を起こさないよう注意しましょう。
高熱が続く場合も受診してくださいね。
高熱ではないけれど発疹で体が熱くなっている時は水やぬるま湯のお風呂で熱さを和らげてあげてましょう。
症状は1週間ぐらいで収まってきます。その間は子供もお母さんもいろいろ大変ですが頑張ってくださいね。
保育園はいつまで休めばいい?
手足口病の感染してから一週間もすれば症状が落ち着いてきます。
落ち着いたら直ぐ、保育園に行ってもいいのでしょうか?
手足口病は感染力は高いのですが、インフルエンザのように出席停止期間がありません。
そのため症状が落ちつけば外出が可能ですが、保育園によっては「完治証明」がなければ登園できない場合があります。小さい子供たちが集団生活するので、感染しないようにという配慮でしょうね。
手足口病にかかった時は保育園にいつから行っていいのか必ず確認してくださいね。
保育園ではなく、他の人に会う場合はどうすればいいのでしょうか。
その場合は、症状が落ち着いて2週間ぐらいたってからにしましょう。症状が落ち着いても2週間ぐらいは呼吸器からウィルスが排出される可能性があるからです。
子供の病気はお互い様と言ったりしますが、やっぱり病気にかかると子供もつらい思いをするので、お互い感染しないように配慮したいですね。
関連サイトインフルエンザの潜伏期間や症状は?検査の方法、休む期間はどうなる?
関連サイトアデノウイルスの症状、熱や目やにの他は?保育園はいつから行ける?
まとめ
今年は手足口病の流行が早まっています。かからないように予防も必要ですが、かかってしまってもあわてないで病院に行きましょう。
痛みを伴うことが多い病気なので、こちら側もつらい思いをしますが、子供ができるだけ快適に過ごせるようにしてあげたいですね。